出版情報PUBLICATION
 著 書
著 書
知財部員のための特許権行使戦術 山内康伸・山内伸著
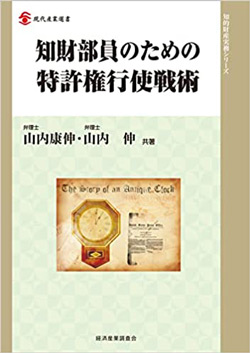
本書は、特許権侵害と各請求権の詳説、紛争の事前対処(異議申立、無効審判など)と事後対応(交渉、ADR、裁判など)について、実務知識やノウハウを紹介したものです。
本書前半は、近年の裁判例を示しつつ、どのような場合に特許権侵害が成立するかを解説しています。また、差止請求や損害賠償請求などの各請求権についても解説しています。特に、損害額の算定については、近年の法改正、裁判例を反映した最新情報であり、実務上役立つものになるよう企図しました。
本書後半の紛争解決に関しては、「戦略と戦術の区別が大事…なぜなら戦略上の誤りを戦術的努力で補うことはできないから」とか、「思わぬ敗訴を避けるために注意すべき観点は…」など、けっこう大胆な話題を取り上げています。しかし、実のところは共著者の一人山内康伸が企業の知財部員だった頃の経験と失敗を思い起こして記述したものです。それだけに現役知財部員の方々には是非知って欲しい実践知か、と思っています。
本書が皆様の日頃の実務遂行に多少なりともお役に立てたら幸甚に存じます。
(経済産業調査会 ISBN978-4-8065-3089-3 定価:5,200円)
目 次
第1章 特許権侵害
1.1 文言侵害
1.2 均等侵害
1.3 間接侵害
1.4 無効理由に基づく権利行使の制限
1.5 特許権の消尽
1.6 先使用権
1.7 特許権の効力が及ばない範囲
1.8 実用新案権侵害
第2章 特許権侵害に対する請求
2.1 差止請求
2.2 損害賠償請求
2.3 不当利得返還請求
2.4 補償金請求
2.5 信用回復措置請求
2.6 標準必須特許の注意点
第3章 特許の成立を争う手続
3.1 紛争の未然の防止
3.2 情報提供
3.3 異議申立制度
3.4 異議申立のシミュレーション
第4章 特許の有効性を判断する手続
4.1 特許の有効性を判断する手続
4.2 無効審判制度の概要
4.3 無効審判の請求
4.4 無効審判において特許権者がとれる応答手続
4.5 無効の抗弁に対する訂正審判の請求
4.6 無効審判のシミュレーション
第5章 無効審判の審決に対する不服申立て
5.1 無効審判の審決に対する取消訴訟の概要
5.2 提訴および原告がとるべき手続
5.3 応訴および被告がとるべき手続
5.4 無効審決取消訴訟のシミュレーション
第6章 紛争を解決するための手順とメニュー
6.1 紛争解決のための準備行動
6.2 警告と当事者間交渉
6.3 裁判外紛争解決手続における調停と仲裁
6.4 裁判所知財調停
6.5 裁判(侵害訴訟)
第7章 特許侵害訴訟当事者本人の役割
7.1 侵害訴訟に必要な判断と準備
7.2 侵害訴訟を始めたときの当事者本人の役割
7.3 侵害訴訟の進行中における当事者本人の役割
7.4 侵害訴訟を終えるときの当事者本人の役割
7.5 侵害訴訟のシミュレーション
裁判例索引
語句索引
裁判例に学ぶ特許権取得戦術 山内康伸・山内伸著
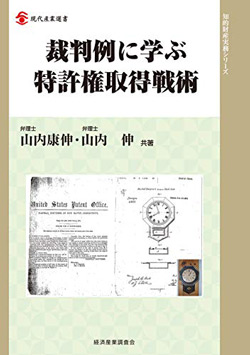
本書は、特許権の取得業務に関わる弁理士、企業・大学の知財部門の方々向けの実務書です。
強い特許を取得するには、様々なスキルが要求されます。暗黙知にある発明を理解するための発明者とのコミュニケーションスキル、発明を特許要件に照らしてまとめ上げる創造スキル、出願手続を遺漏なく進める手続スキル、特許審査で特許性を認めてもらうための説得スキル、などです。
これらのスキルを自分の経験だけで積み上げるには限界があります。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」ということわざがありますが、他者の経験知も参考にすべし、というのが真意と思います。
特許実務の世界で、他者の経験知は裁判例に現れています。裁判例は多くのことを教えてくれます。学ぶに如くはありません。多くの経験知を取り込み、特許権の取得戦術を磨きましょう。
本書が、このような趣旨で使って頂けますなら、著者の望外の喜びとするものであります。
(経済産業調査会 ISBN978-4-8060-2 4,500円)
目 次
第1章 特許要件
1.1 発明該当性
1.2 新規性
1.3 進歩性
1.4 拡大先願
1.5 先願
1.6 実施可能要件
1.7 サポート要件
1.8 明確性要件
第2章 強い特許を取る出願戦術
2.1 発明の把握の仕方
2.2 発明の思想性と出願手続上の関わり
2.3 明細書の記載ルール
2.4 明細書等の書き方
2.5 裁判例からみた強い明細書
第3章 特許を取得するための手続
3.1 出願
3.2 出願前の一般的注意事項
3.3 国内優先出願の活用
3.4 出願審査の請求
3.5 優先審査と早期審査
第4章 拒絶理由通知に対する応答
4.1 審査の進め方と出願人がとれる対応
4.2 最初の拒絶理由通知と対策の検討
4.3 明細書等の補正と最初の拒絶理由通知に対する反論
4.4 最後の拒絶理由通知と対策の検討
4.5 明細書等の補正と最後の拒絶理由通知に対する反論
4.6 分割出願
4.7 面接審査
4.8 拒絶理由通知に対する応答シミュレーション
第5章 拒絶査定に対する応答
5.1 拒絶査定不服審判の審理
5.2 拒絶査定と対策の検討
5.3 明細書等の補正と審判請求書による反論
5.4 拒絶理由通知と拒絶理由通知に対する反論
5.5 出願の変更
5.6 拒絶査定不服審判の請求シミュレーション
第6章 拒絶審決に対する応答
6.1 拒絶審決に対する不服申立
6.2 審決取消事由
6.3 訴の提起と原告の主張
6.4 訴訟手続と原告のなすべきこと
6.5 判決
6.6 審決取消訴訟のシミュレーション
第7章 出願経過が権利行使時にどう参酌されるか
7.1 出願経過が参酌される場面
7.2 中間書類のドラフト上の注意事項
裁判例索引
語句索引

